
育児に励む人
- 現在育児の真っ只中
- 子供の才能を伸ばしたい
- 頭の良い子に育つ方法は?
こんな悩みを解決します。
【結論】子供の才能は習慣で開花する。
頭の良い子に育つかどうかは小さな頃から何を習慣にしてきたかで決まります。

この記事のもくじ(クリックでジャンプ)
子供の才能を伸ばす習慣5つ

イチローやタイガーウッズなど、天才は子供の頃から才能磨きが生活の一部でした。
ダルビッシュの父親は、まだダルビッシュがハイハイしていた頃、野球、バスケット、テニスなどのボールを与えて最も気に入ったものをやらせようと決めたそうです。
名だたるF1ドライバーたちも子供の頃からカート遊びが日課。
才能は幼少の過ごし方で決まります。
天才と呼ばれるレベルを目指さなくても、有能である方が人生は楽。
ならば子供にはできる限り才能を伸ばす関わり方をしてあげた方がいいですね。

①褒めて育てる

英国で行われた有名な研究結果の話。
某小学校で、無作為に選んだ生徒たちを「優秀クラス」として分け、「一般クラス」との成績を比べるというもの。
結果は優秀クラスに振り分けられた生徒たちは一般クラスよりも平均20%以上成績が良かったそうです。
注目すべきは成績が良いから褒めたのではなく、先に「君たちは非常に優秀だから特別クラス扱いだ」と褒めたから成績が向上したという点。
大人から褒められた子供はセルフイメージが上がって才能を遺憾なく発揮します。
日本人は特に他人を褒めるのが苦手な人種で、優秀でも褒めない人が少なくありません。
褒めるだけで才能が開花するのだから、今すぐ始めた方がお得。
豊臣秀吉は足軽から天下人へと登り詰めましたが、彼は人を褒める達人だったといいます。
優秀な人材は褒めてくれる人のところへ集まるから。
毎日褒められて育った子は自分を大切にし、自信を持って行動できる子に育ちます。

②毎晩絵本を読み聞かせる
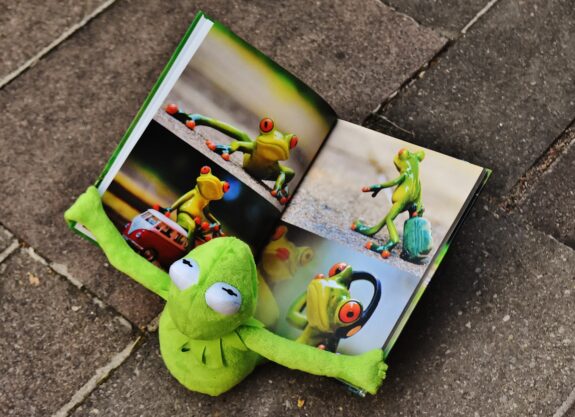
最高の育児法は毎日絵本を読み聞かせること、といわれるほどその効果は抜群。
親子のコミュニケーションも深まるし、子供は将来本好きになって必ず頭の良い子に育ちます。
できれば毎日5冊読み聞かせるのが理想。
絵本は繰り返し読む前提で作られているので毎日同じ本でも問題ありません。
読書なしに大成功した人は皆無。
ちなみに我が家の子供によく読み聞かせたのがあいしているから (児童図書館・絵本の部屋)これ。
嫁は子供にこれを読み聞かせる時いつも泣いてました。

③外遊びをさせる

現在は外遊びをさせにくい環境になりました。
私が子供の頃はファミコンが出るまで外遊びが基本。
虫取りや探検隊ごっこ、野球やサッカー、缶蹴りにメンコ、ラジオン、ミニ四駆。
今では安全に遊べる場所も少なく、遊び方を知らない子供も多いですね。
外遊びは想像力を育む道場。
ビー玉なんてただのガラス玉なのに、当時の子供たちは無数の遊び方を考え出して楽しんだものです。
今の子は独自アイデアがなく、なんでもネット検索して真似るだけ。
安全は第一ですが、外遊びの経験は間違いなく社会に出ても役立ちます。
休日に家族で公園遊びを習慣にするだけでも子供の心は踊るはず。

④最新機器を与える

外遊びと逆説に感じるかもしれませんが違います。
最新機器には早めに触れさせておくべき。
私はファミコン世代ですが、発売日に買ってずっとファミコンをしていた弟に比べて、私は小学校高学年くらいでファミコンデビュー。
結果、大人になっても私は機械が苦手でパソコン音痴ですが、弟はパソコンが得意です。
弟曰く、わざわざ使い方を調べなくても何となく勘でわかると言ってました。
小さい頃からゲーム機やビデオデッキなど何でもイジっていた結果といえるでしょう。
自転車に乗れると乗れない頃に戻れないのと同じ理屈。
一度身に付けたバランス感覚は他でも応用できるというわけですね。
但し、弟は完全引きこもり野郎だったので運動神経が悪いし発想力も語彙力もありませんがw

-

-
子供と遊べるカードゲームおすすめ10選【スマホアプリより面白い】
おうち時間を楽しみたい スマホ時間を減らしたい カードゲームは楽しい? 家族で楽しめるやつ教えて こんな要望にお応えします! 【結論】複数人で遊ぶカードゲームは1人でやるスマホゲームより断然面 ...
続きを見る
-

-
家族で楽しむボードゲームおすすめ5選【子供の脳トレにも最高】
かけだしボードゲーマー スマホやSwitchに飽きた 画面の見すぎで視力が心配 家族団欒の時間を持ちたい お薦めのボードゲームは? こんな悩みを解決します! ゲームの歴史を辿るとボードゲー ...
続きを見る
⑤動物の世話をさせる

イギリスのことわざに次のようなものがあります。
子供が生まれたら犬を飼いなさない。
- 子供が赤ん坊のときは良き守り手となり
- 子供が幼いときは良き遊び相手に
- 子供が少年期のときは良き理解者になるだろう
- そして子供が青年になった時、犬は自らの死をもって命の尊さを教える
小さい頃から動物の世話をさせると、自分のお世話をしてくれるママに感謝の気持ちも湧くはずです。
別に犬でなく小動物でもいいでしょう。
名前も子供に付けさせて、可能な限り自分で管理させること。

子供の才能を潰す習慣3つ

子供の才能や性格を無自覚に歪めている親は多いです。
私も何度も反省しながら育児を続けてきました。
ここからは子供に対してNGな行動を3つ解説します。
思い当たるフシがあれば今すぐ改善するべき行動3つ。

①否定、指摘、心配する
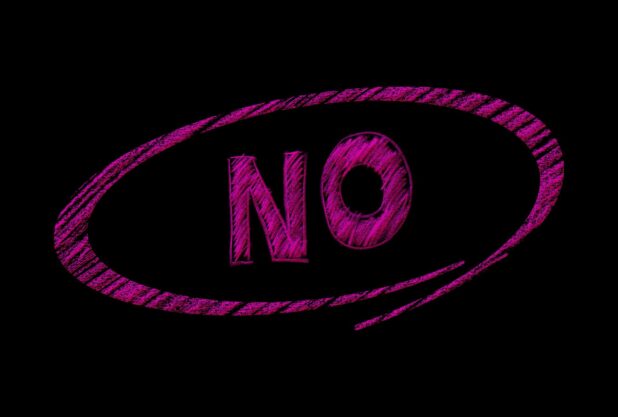
「違う」「ダメ」「うるさい」
毎日このような言葉を浴びせられて育った子は将来自分を大切にしなくなります。
親に否定されて育つと潜在意識に自己否定が定着するのは必然。
自己否定の最悪のケースが自殺であり、自らの身体を売る行為です。
親に大切に育ててもらった身体を粗末にする心は病気以外の何ものでもありません。
すべては親から受けた否定が原因。
子供の事を思うからこそだと思いますが、伝え方には常に愛情と気配りが必要ですね。
加えて、「うるさい」も控えたほうが賢明です。
大きな鳴き声が出せない赤ちゃんはいませんが、自分の意見を大きな声で言えない子は沢山います。
赤ちゃんの頃は出ていた声が歳を重ねると出せなくなる、すべては親から浴びた言葉という後天的な原因。
酷い子の場合「どもり」を患うケースも。
近所迷惑を躾ける事と、うるさいからと黙らせるのは別。
さらには心配のしすぎも問題です。
大切に思うから心配するのだと思いがちですが、心配とは信頼していないことの証明。
心配な気持ちをグッと堪えて「お母さんはいつも信じてるからね」と言ってあげましょう。
そんな言葉を受けて育った子が親を悲しませるような事をするはずがありません。
子供は常に親が見ていない時に成長します。
頑張って子供を信じてあげてください。私も頑張ります。
②ゲームを禁止する

ゲームのハマりすぎは良くないですが、全く触れさせないのはもっと良くないです。
今日生まれた子供が将来働くとき、現在存在しない職業に就く確率は65%。
ダボス会議という、世界の有識者たちが割り出した数字なので信頼性は高いです。
例えばユーチューバーやクリエイター。
現在のユーチューバーたちは全員彼らが生まれた頃まだYouTubeどころか、ネット普及率も一桁台でした。
今後はこの流れがさらに加速し、今ある職業のほとんどは新しく生まれ変わります。
将来はもっとゲーム感覚で働く時代になると予想されているのです。
そんな未来を知りつつ、ゲームを禁止して育てるのは子供の才能に蓋をするのと同じ。
ゲームは軍事や宇宙開発に次ぐ早さで最先端技術が導入される業界。

③習い事漬けにする

子供に一週間ぶっ続けで習い事をさせる親は教育テロリストです。
うちの息子の友達に火曜日以外ぜんぶ習い事で埋まっている女の子がいましたが、正直言って可哀想なくらい無能でした。
息子が幼少の頃、七田の右脳学校に通っていてその子と同じクラスでしたが、一番落ちこぼれだったのがその子。
教室が終わればすぐにまた次の習い事へと連れて行かれる毎日。
小学校に上がる寸前でも、その子はまだ平仮名で自分の名前が書けないレベル。
子供の脳は吸収しやすいと勘違いして無理に詰め込んでも逆効果です。
親の自己満足なスパルタ教育の典型でしたね。
その子はいつも親の期待でプレッシャーに泣いていたのを憶えてます。
ちなみにその子のお兄ちゃんは「アスペルガー」を患いカウンセリングに通う日々。
それでもその子が古事記の暗唱大会で優勝したことを自慢気に話すお母さんの無神経さには呆れを通り越して恐怖を感じました。
本人は親のせいでアスペルガーになったことを知らず、親の言いなりで永遠と習い事を続けるだけ。
どんなに記憶力が良くても、将来も同じく他人から言われたことを憶え、言われた事だけをやる人間にしかなれないでしょう。
親の都合で習い事を詰め込む行為は絶対にNG。
「子供のためを思って」
このセリフを言う親に本当に子供を思う心はありません。
お互い、大切な子供を元気に伸び伸びと幸せに育てたいものですね。
頑張りましょう。
-

-
スマホ依存症の対策と治し方3つ【スマホ離れしてはいけない】
スマホ依存症なのかな・・・ スマホを眺める時間が長い スマホなしでは生きれない 子供のスマホは制限すべき? こんな悩みを解決します! 【結論】スマホ依存症の脱却とはスマホを完全に使いこなすこと ...
続きを見る
-

-
ゲームに課金する子供は将来ギャンブル依存症になる【3つの対策】
悩める親御さん 子供がゲームに夢中 最近課金したがるようになった 課金はさせない方がいい? こんな悩みを解決します! 【結論】ゲームに課金する人の心理状態はギャンブル依存症と全く同じ。 お ...
続きを見る


